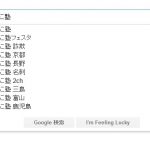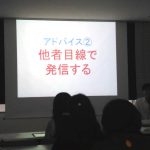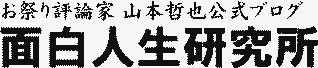お友達のイベントに、「仲居さん」のコスプレでお手伝いに。
そこでよく聞かれることが「仲居さんの衣装、どこで売ってるの?」という質問です。今回はそれにお答えしました。次回からは、この記事のURLを示してお答えします。
ただ実際、仲居用の着物を買いたい人よりも、「どうすれば仲居さんみたいに見えない着物の着こなしができるのか?」という声のほうが大きいかもしれません。
仲居さんになる人も、なりたくない人も(笑)、この記事がヒントになればさいわいです。
ちなみに、「仲居さん着物セット」みたいなものも一応あることにはあるのですが、巫女や町娘のように、パーティーグッズ専門店で安価なコスプレ用仲居衣装セットが売られているなんてことはありません。
旅館や料亭などでお勤めする本職の仲居さんなら、着物と帯くらいは旅館やお店から貸与されるでしょう。ただ、足袋や長襦袢など個人的な小物は自己負担というところが多いですが。
私の場合は、リサイクル着物店とか、ヤフオクとか、前掛けやタスキなど小物は道具屋筋の白衣屋さん(業務用エプロンなどを売ってる店)や、船場センタービル地下の着物やさんなどで一品ごとに少しづつ買い揃えていったわけです。
着物
色無地が一般的です。
ときには、細かい模様の小紋が使われることもあります。
そば屋や民芸風居酒屋だと、絣の着物を用いることもあります。
仲居さん着物に求められる条件は、
丈夫なこと
お洗濯できることと
濡れたり汚れたりしても平気なこと
衣装が目立たないこと
です。
1000円のリサイクル着物など、いろいろ試してみましたが、丈夫で、洗っても型崩れしないことから、この着物が一番おすすめ。
新品・しかも送料無料でこの値段は驚き!
6月~9月は、「単衣(ひとえ)」と呼ばれる、裏地のない着物を用います。
ちなみに仲居さん用の色無地着物には、「紋」を通常入れません。その人しか着られなくなりユニフォームとして使い回しができなくなるからです。
一つ紋色無地が好まれる「茶道の着物」とは、そこが違うところです。
帯
仲居さんらしさを追及するなら、やっぱり名古屋帯の無地。模様は(遠目には無地っぽく見える)地模様くらいが許容範囲。逆に言えば、柄がはいっていたり、豪華な袋帯だと、仲居さんに見えない帯のチョイスとなるようです。色無地が制服みたいになっている茶道の方の参考になればさいわいです。
色は白が、どんな色の着物にも合わせやすくて最適。紺色・青色やピンク・黄色の着物だと、赤色の帯もよく似合います。
たとえば、こんな感じの帯が定番です。
袋名古屋帯(仕立上り) 【代引手数料&送料無料】 麻の葉 上品でお着物に合わせや…
|
リンク先の帯、付け帯加工がオプションになってますが、つけることをおすすめします。着付けがだいぶ楽になります。
黄色は、紺色無地にあわせてもそれなりに似合うようですが、むしろ茶摘衣装や早乙女のように、絣の着物にあわせたいところです。

長じゅばん
着物の下に着る、一種の下着。
これがないと、白い半襟をつけるところがありません。(笑)
業務用だと、こんなのがお手ごろかも。
足袋
仲居さんなら、白足袋一択です。
黒や紺色は通常「男物」ですし、レース足袋や柄足袋だと、とたんに仲居さんらしく見えなくなります。
前掛け
汚れ防止・着物のすり減り防止という実用的観点だけでなく、前掛けしていると働き者らしくみえます。
たすき
わんこそばのお店や、馬車道や、何とか農場の制服で「たすき掛けが標準の制服」だと別ですが、通常の仲居さんだと、通常たすき掛けのままお客さんの前には出てこないようです。
裏でお掃除や洗いものをするとき、腰紐でたすき掛けするのが多いです。
実用的には、腰紐を1本余計に買ってそれをたすきにすればいいですが、見せるたすきを必要とするなら、こんなのはいかが?
本職の仲居さんの場合、背中のバッテンを見せない、帯の中に潜らせて使う、このようなたすきを使うようです。先日、がんこ寿司へ行ったときも、このようなひもを使ってました。(ひょっとしたらコーリンベルトで引っ張ってたのかな?)
「タスキット」は商品名かな?
履物・着付け小物など
あと、帯締め・帯揚げ・履物(ぞうり)など、着付け用具がたくさんあります。
ちなみに帯締めは「100均手芸コーナーに売ってたエプロンひも」、帯揚げは「晒しを適当な長さに切ったもの」を流用しました。
男がコスプレ的にやる場合、履物(の寸法)が問題ですが、ここにあるような、白鼻緒の雪駄を利用すれば、それらしく見えるでしょう。
母親など、家族で着物を着る人がいる場合、そういう着付け道具を持っているはずなので、協力してもらえるかもしれません。
====================================================================お祭り評論家 山本哲也の提供するサービス
1.お祭り専門メディアの制作・運営
2.新聞・雑誌などでの企画協力(インタビュー)
3.テレビ・ラジオの出演
4.お祭りに関する記事の執筆
5.講演・セミナー講師(当面の間オンラインで対応)
6.その他、日本の祭りに関すること(お気軽にご相談ください)
■ 取材・講演等、お仕事のご依頼・お問い合せはこちら:お問い合せフォーム

今までのメディア掲載・出演実績はこちら。